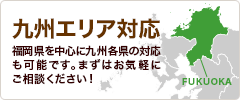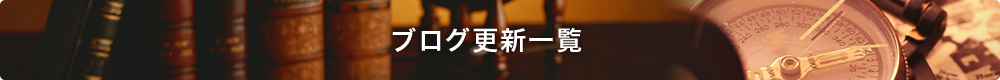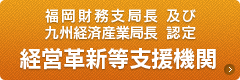経営改善ブログ
[2024.8.24]
カテゴリー:M&A
金融機関から融資を受ける際に付けられる「経営者保証」は、中小企業のスモールM&Aの際によく課題となります。
この点について、一般的な処理方法とM&A時に売手企業の経営者が注意すべき点を以下にまとめます。
M&Aの際、売手企業の経営者は金融機関に対して経営者保証の解除を求めるのが一般的です。
買手企業の経営者に対して保証を付け替えるか、もしくはかなりハードルは高いですが、経営者保証なしで融資を継続するよう交渉します。
買手企業の経営者が経営者保証を引き継ぐ場合でも金融機関との協議が必要であり、買手企業や新しい経営者の信用力が重要となります。また、売手企業の既存融資を買手企業が、一旦、全額返済して売手企業の経営者の経営者保証を解除し、その上で買手企業が新規の融資を受けるケースもあります。
売手企業の経営者が注意すべき点としては、金融機関と経営者保証の扱いについて早めに協議することが重要です。
金融機関の意向を確認し、スムーズな移行を図ります。しかし、余りに早く、M&A初期の段階で金融機関に相談すると、
思わぬ横やりが入ったりすることもありますので、個人的には買手企業と概ね基本合意契約を締結する前くらいのタイミングが良いのではないかと思います。
また、経営者保証に関する取り扱いについては、M&A契約書に明記します。具体的な処理方法、責任の所在、解除手続きの進行状況などを詳細に記載します。そのためには、弁護士やM&Aアドバイザーなどの専門家を活用し、金融機関との交渉や契約書の作成を円滑に進めることが重要です。専門家の助言を得ることで、最適な解決策を見つけることができます。
当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
中小企業経営者の高齢化と後継者不在の中で、自社を他社に譲渡(売却)するM&Aが注目され、活発に行われるようになっています。
いわゆる、スモールM&Aが活発になることにより、事業として参入する事業者が増えてきています。
一方、市場、プレイヤーの拡大により、様々な問題が発生しています。
例えば
・M&A仲介業者が買手に有利な価格でまとめた
・仲介業者に納得のいかない手数料を支払った
・買収後にわからなかった(帳簿外)の債務(借金)が発覚した
・残業手当の未払いがあり、辞めた従業員から訴えられた
・取引先と期待していた大手商社がM&Aにより契約上取引ができなくなった
等など多くの事例があります。
上記の中には、買手側が「財務・事業・法務」などの面の、いわゆる買収監査(デューデリジェンス:DD)を行って隠れている問題を探しますが、小規模(少額)なM&Aの場合は、このDDを費用の面で十分に実施していない場合が多いです。
M&Aを検討している経営者の方は、M&Aの基本的な取組みを示し中小企業庁が推進している、「M&A取引の健全化策(中小M&Aガイドライン(第2版))」とM&A業界が取組みを開始した「自主規制ルール」について、是非、事前にご確認をしていただきたいと思います。
当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
今年も残すところ僅か1週間となりましたが、今年もコロナに始まりコロナで終わるような一年でした。
「コロナ禍」と言われ出して約3年経過していますが、まだ、明確な出口は見えていないように思います。
一斉に経済に悪影響を与えたコロナ禍は、経営コンサルタントである私にも大きく影響を与えることになりました。
普段は、企業の再生支援を行っているのですが、新型コロナ特例リスケジュール計画策定支援やセーフティネットの借入など、支援の案件が一気に増えました。ただ、私を含め経営者の方々においては、ここまで長期化するとは思っておらず、さらに、終わりの見えない状況の中、経営に不安を感じる経営者はもっと増えてくると思います。
一方で、「LLP福岡事業承継・M&Aセンター」https://f-bsma.jp/の代表を務めていますので、事業承継やM&Aについてのご相談の多く受けておりまして、買収に精力に動いている元気な会社もあります。
5年前に国は、中小企業の事業承継等を集中的に支援を実施していく「事業承継5ヶ年計画」を策定しました。
5年経過して事業承継補助金等の様々な施策が生まれ、このコロナ禍を契機として、中小企業の事業承継の出口戦略として第3者による事業承継、いわゆるM&Aが一気に進んでいくのではないかと思います。
経営者の皆さんが一番気にしてあることは従業員の雇用です。雇用維持のためにも、現在の経営者や創業者に対し、事業承継の必要性と意義に気付いてもらうことが第一です。
当センターの活動が少しでも地域経済の活性化につながりますよう、経営コンサルタントとして、その責務を果たすべく、来年も更なる飛躍を目指してまいりたいと思っております。
来年も、何卒よろしくお願い申し上げます。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
11月19日(土)、20日(日)に、LLP福岡事業承継・M&Aセンターが主催する『第9回事業承継・M&Aアドバイザー養成講座』を開講いたしました。
今回、新たに 22名の『事業承継・M&Aアドバイザー』が誕生しました。
皆様、土日の2日間みっちり終日の講座の受講、お疲れ様でした。
※ 1日目の講座終了後の交流会での皆様の和やかな笑顔の写真も掲載させていただきます。
本講座は、LLP福岡事業承継・M&Aセンターに所属しているメンバーが、その専門の内容の実例を交えながら、進めていきます。
講師であるメンバーは全員、国家資格所有者であり、また、実務経験者であるため、ここでしか聞くことのできない実体験を交えた講義を聞くことができると大変好評を得ています。
今までの受講生は、士業の方が多くいらっしゃいました。やはり、日頃から顧問や支援を行ってある企業様へのサービス向上や、業務拡大の一手にできるからであると思われます。
しかし、最近では、企業の方や金融機関の方の受講が増えてきています。企業の方においてはM&Aへの関心の高まり、金融機関の方においては日頃の業務で活用することができるためであると思われます。
事業承継をするにはどうしたらいいのか、そろそろ誰かに譲りたいが後継者がいない等、相談する相手がいない孤独な経営者に寄り添えるアドバイザーを養成することで、中小企業を元気にし、地域に貢献していきたいと思っています。
また、事業承継やM&Aについて悩んでいる経営者・企業様向けには、令和5年1月18日(水)に無料セミナーを予定しております。無料相談会も行いますので、是非ご参加ください。
https://f-bsma.jp/seminar/
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
[2022.10.29]
カテゴリー:M&A
今回も、前回の続きとして「中小M&A推進計画」の主なポイントを解説させていただきますので、是非、ご覧ください。
中小M&Aに関する基盤構築のための取り組み
企業において、事業承継は早い段階から計画的に進めることが重要です。
しかし事業承継は、他の経営課題よりも後回しにされ、対応が遅れてしまうことが多い傾向にあります。また、中小M&Aの拡大に伴って支援機関も増加するなかで、中小企業が適切な支援を選択できず、トラブルが発生することも多くなっています。
そこで、以下の対策が講じられました。
「事業承継診断」から「企業健康診断」へ
現在も、事業承継ネットワークによって事業承継診断の取り組みが進められていますが、事業承継診断票や事業承継計画が簡素であることから、実際に支援に活用するには不十分であることが問題として挙げられています。
そこで、2021~2022年度中にナッジ(=行動経済学)の活用や企業価値評価ツールとの連携が検討されます。事業承継を意識したときだけでなく、常日頃から企業価値を把握できるよう「企業健康診断」の作成・試行が行われます。
その上で、2023年度以降は、全国の事業承継・引継ぎ支援センターや事業承継ネットワーク構成機関にて企業健康診断の提供を行っていきます。
M&A支援機関の登録制度を創設
中小M&Aの拡大に伴い、知見やノウハウが十分でないM&A支援機関の参入が懸念されています。また、M&Aに関する知識が乏しい企業にとっては、適切な支援を選択できないことが問題となっています。
この点においては、2020年3月に「中小M&Aガイドライン」が策定され、以下のことが明示・規定されています。
・M&Aの基本的事項を明示
・手数料の目安を明示
・M&A業者における適切なM&Aのための行動指針を策定
・利益情報の開示など、利益相反のリスクの最小化を規定
・セカンドオピニオンの推奨を規定
そして今回の「中小M&A推進計画」において、新たに以下の取り組みが策定されました。
- M&A 支援機関に係る登録制度等の創設
- M&A 仲介等に係る自主規制団体の設立
まず「M&A支援機関に係る登録制度等の創設」として、2021年度中に、中小M&Aガイドラインの遵守を要件としたM&A支援機関の登録制度が創設されます。そして、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)においては、(中小企業庁)登録済みのM&A支援機関を活用した場合のみ、費用の補助が行われます。
次に「M&A仲介等に係る自主規制団体の設立」については、中小企業の保護と中小M&A 仲介の公正・円滑な取引を目的として、中小M&A仲介業者を会員とする自主規制団体が2021年度中に設立されます。
そして、設立後は以下の活動を行うことにより、中小企業が安心して支援を受けられる環境を整えていきます。
・中小 M&A ガイドラインを含む適正な取引ルールの徹底
・中小 M&A ガイドラインの遵守の義務づけ
・M&A支援人材の育成のサポート
・仲介に係る苦情相談窓口の設置
まとめ
事業継承そしてM&Aを完遂するためには、専門的知識が必要不可欠です。
今回取りまとめられた「中小M&A推進計画」において、転廃業や事業継承を考えている中小企業が事業承継・引継ぎ支援センターに相談をした場合、相談から専門家の紹介までノンストップで支援を行っていくことが策定されました。
私が代表を務めます、「LLP福岡事業承継・M&Aセンター」も中小M&Aをワンストップで支援させていただいています。
また、安部中小企業診断士事務所も「中小企業庁登録 M&A支援機関」として、中小企業のM&Aを支援させていただいています。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
カテゴリー
月刊アーカイブ
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月