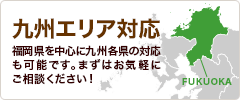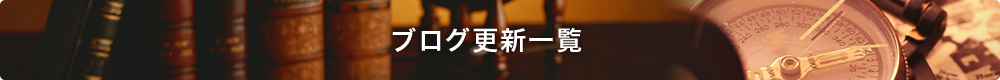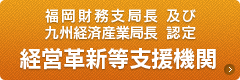経営改善ブログ
[2014.4.19]
カテゴリー:セミナー
先日、「中小企業診断士の魅力と資格の活用」と言うテーマで
セミナー講師をさせて頂きました。
診断士を目指す方向けの予定でしたが
現役の診断士の方も多数ご参加いただき
非常に緊張いたしました。
ところで、「中小企業診断士」とは中小企業支援法第11条に基づき
経済産業大臣が認定し登録する経営コンサルタント唯一の国家資格です。
また、マネジメント全般の高度な知識を有し
企業経営全般を総合的な視点から分析し
企業経営をサポートすることができる専門家として位置づけられています。
一言でいえば、「中小企業を支援する経営コンサルタントの国家資格」
と言うことになります。
診断士になるためには、7科目の1次試験に合格したのち
2次試験に合格するか、中小企業大学校か登録養成機関が実施する
養成課程を修了する必要があります。
1次試験の合格率は20%前後、2次試験の合格率も20%前後ですので
試験での「中小企業診断士」の合格率は、4%前後となります。
それでは、中小企業大学校か登録養成機関に進んだ方が良いか
と言うと、そんなに甘くありません。
当然、入学するための選抜試験もありますし、修了試験もあります。
またなんといっても、多くの時間とお金が掛かります。
企業から派遣される方は良いでしょうが、一般企業にお勤めの方は
現実的に困難ではないでしょうか?
登録養成機関には大学院が多いので、社会人用のプログラムやカリキュラムが
用意されていますが、2年間も必要です。また、中国地区や九州地区には
登録養成機関がありません。
ですので、仕事を辞めて中小企業大学校や登録養成機関に
進まれて勉強をされている方も多いようです。
そんな資格ではありますが、最近は受験者も増えているようです。
1月7日付の日経新聞によりますと、「仕事に役立つ資格」の1位となっています。
また、「取りたい資格」の3位となっています。
実際に今回のセミナーも30代~50代と幅広いビジネスパーソンの皆様にご参加いただきました。
資格取得の目的は、皆様それぞれのようでしたが
熱心に話を聞いていただきました。
資格の活用についても話をさせて頂きましたが
またの機会にブログにアップしたいと思います。
[2014.4.8]
カテゴリー:人材育成
桜のピークも過ぎ、温かい日差しが心地よい時期になってきました。
新年度もスタートし、新入社員が新しい風を吹き込んでいる会社も多いのではないでしょうか?
そこで今回は旬な話題、人材教育について考えたいと思います。
人材教育と言っても新入社員教育から営業社員教育・幹部教育まで幅が広いですが、弊所が経営コンサルティングをする場合に、企業様に人材教育の重要性を訴えかけるには理由があります。
一般的に”大手企業・上場企業”と言われる企業と”中小企業”と言われる企業、組織として両者ともに一長一短ございますが、業務を行う上で最も温度差を感じるのは、この人材教育に対する取組みです。
大手企業・上場企業では当たり前のように行われている人材教育や優秀な人材の確保。
莫大な時間と費用をかけてでも行うのはなぜでしょうか?
お金があるから?時間があるから?形式上?宣伝のため?
いいえ違います。
あえてそこにお金と時間を注いでいるのです。
その理由は、例えば新入社員教育であれば以下のようなものです。
①業務を安心して任せられる様にするため
②自分たちが会社の看板を背負う責任を熟知させるため
③会社の看板を背負うのにふさわしい人材になってもらうため
まだまだ、他にも理由はあります。
特にお客様や取引先その他外部との接触をもつ社員は、お客様や外部の方からすれば、その担当者が会社の顔になり、その担当者のイメージが会社のイメージに直結します。
大手企業・上場企業は、長年の経営の実績の中で人材育成がいかに業績へ影響を及ぼす”重要な課題”であるかをよく理解しているのです。
大手企業・上場企業は顧客に対する責任だけでなく、社会に対する責任、株主に対する責任、取引先に対する責任と色々な責任を負ってます。責任を負ってるのは中小企業も同じですが、大手企業・上場企業は社会的役割の大きさ、社会的責任の重さ、注目の高さなどに比例して強い危機管理をもって業務を遂行しています。
ですので、実際に現場で業務にあたる社員の責任感や仕事に対する姿勢を、入社時より徹底的に教育をしているのです。
解りやすい例を挙げるとすれば、航空会社。
担当者のミスで『入力ミスして、飛行機遅れます』とか『飛行機の故障に気が付きませんでした』とか『個人情報漏洩してしまいました』なんてことは、万一にもあってはならないのです。
これが何度も起こってしまえば、会社の死活問題です。なぜなら、定刻出発や安全や信頼は商品の一部で、そんなことは最低限のルールだからと言う認識からです。落ちるかもしれない危険な飛行機、時間も守れない飛行機、信頼を簡単に裏切る会社であれば誰も乗りたがらないでしょう。こんなことが守れないようでは顧客満足など得られるわけありません。
ですので、もちろん業務を行う担当者達は一瞬たりとも気の抜けない状況で業務にあたります。
一見そうは見えませんが、現場はすごい緊張感で業務を行っているのです。
1便1便を、限られた時間内に定刻で安全に落ち度なく出発させるために必死で業務にあたります。
食品会社なども同じですね。
『間違って髪の毛が入ってしまいました』など許されません。
『衛生状態を疑うな~。そんな会社の商品は信頼できないな~!』と思うのが顧客心理です。
他業種であっても同じことが言えるでしょう。
日本人の仕事の丁寧さや迅速さ正確さサービスの良さなどは、世界も認めるところで、それは日本が世界に誇る財産でもあります。
だからこそ、業務に対する姿勢を入社したと同時に教育を行う必要があるのです。
しかし、現代の大手企業・上場企業だって初めからその様な大きな会社であったわけでもないし、教育のノウハウを持っていたわけでもありません。数多いクレームや失敗と改良を重ねながらノウハウを生み出したてきたのです。(一部、もともと資金力のあった会社もありますが......)
長きにわたりトップを走り続けている企業は共通して優れた人材教育のシステムを持っています。
素晴らしい人材を育て、顧客の支持を得てきたからこそ今があるのです。
もちろん、中小企業の経営と、大手企業の経営とでは資金力も時間的余裕も違います。
ですが、やはり大企業に学ぶところは多々あると思います。
資金と時間を調整して、できる範囲内でも、あえて人材育成には力を入れた方が良いと考えます。
特に新入社員は、白いキャンバスです。
教育次第でいかようにも描ける柔軟さと夢や希望を持っています。
具体的な教育方法については、ブログで掲載するには大量すぎるので、ここでは、その考え方のみの掲載にとどめたいと思います。
昨今、OJTにおける上司の教える力量不足なども大きな課題になっているようです。絶対に勘違いしてはいけないのは、”教育”とはあくまでも、教え育てることであり"怒る”ことではありません。感情にまかせた文句や説教など論外です。その表現の方法もとても重要です。
新入社員や若い人に『何が解らない?』と聞くと、『何が解らないかが解らない。』と言う返答が返ってくることがよくあります。経験のないことが解らないのは当然のことなのです。その目線まで下りて『何が解らないのかを解る。』レベルまで育てるのが初めの一歩です。
質の高い教育をして、仕事を安心して任せられる、素晴らしい次世代の人材が育っていくように願います。
そして、会社に居るのが一番楽しい!!と社員が思えるくらい、会社や仕事が楽しくなれば、益々、業績は上がるに違いありません。
カテゴリー
月刊アーカイブ
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月