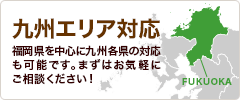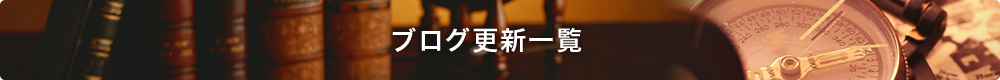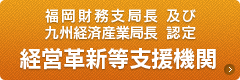経営改善ブログ
2018年6月に成立した、いわゆる働き方改革関連法(正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)に基づいて、2019年4月より労働関係法が順次改正されています。法によって改正時期は異なっており、最初は大企業だけに適用されて、中小企業には遅れて適用されるものもあります。
今回のブログでは、2022年4月以降の中小企業に関する法改正等の概要について少し話をしたいと思います。
対応が遅れると法令違反に問われることもあります。また、若年層の働き手が減る中で、中小企業でもきちんと法令を遵守して働きやすい環境を整えることは、採用・雇用維持対策としても大切です。
最初に、働き方改革の目的と中小企業への影響などについて解説します。
働き方改革の目的は、「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」ことです。
働き方改革が求められる背景には、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「働く人のニーズの多様化」などがあります。人手不足が進む中で、長時間労働の常態化や労働条件のミスマッチなどにより労働者が望む仕事に就けないというケースもあるからです。
企業の生産性を上げて長時間労働を是正したり、短時間労働や在宅勤務など時間や場所にとらわれない働き方を選択できるようにしたりすることで、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが、働き方改革が目指すところです。
中小企業が働き方改革に取り組まなければならない理由は、当然ながら、法令だからです。働き方改革法は2019年4月から順次施行されています。中小企業には遅れて適用される改正もありますが、猶予期間も終わり2022年度に実施または2023年度から実施のものも多数あります。
中小企業がこれらの法改正への対応を怠ると、中小企業も法令違反に問われかねません。
しかし、「法律だから仕方なくやる」というだけではありません。見方を変えれば、慢性的な人手不足や労働生産性の低さなどの、自社の課題を解決し、経営の競争優位性を築くきっかけにもなるのです。
働き方改革によって中小企業はさまざまな対応を迫られます。対応が遅れると法令違反となる可能性もあるため、事前にきちんと準備して社内の環境整備をすすめましょう。
文面の関係もあり詳細は割愛させていただきますが、もし、ご興味のある方は弊所までお問い合せください。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
福岡県は緊急事態宣言も解除されました。コロナワクチンの接種も、徐々に拡大しており、コロナ以前とはいかないまでも、少しずつ経済が回復してきているのを感じます。
さて、今年4月に高年齢雇用安定法が改正されたことをご存じですか。
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。
就業確保措置とは、下記のとおりです。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
今までは65歳までの雇用確保措置は義務付けられていました。
改正法では、雇用確保ではなく、就業確保措置となっています。
というのも、④と⑤のように、自社での雇用ではない措置が加えられているためです。
高齢者の体力、運動能力、健康状態は個人により大きく異なります。また、バリバリ頑張りたい、孫の面倒でも見ながらゆっくり働きたいなどといったライフ・ワーク・バランスに対する考え方もそれぞれ異なります。
各人の希望や様々な状況に合わせて勤務形態、労働日数・労働時間などを見直していくことが必要です。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による「65歳超雇用推進助成金」も準備されていますので
計画的に進めていくことが肝要と思われます。
人生100円時代に備えて、元気な高齢者を支援していきます。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
今年は、桜が早く咲く予報ですね。
毎年、お花見を楽しみしているのですが、今年は密を避け、散歩しながらのお花見になるのでしょうか。
福岡では、緊急事態宣言も解除されましたが、営業時間の短縮は引き続き行われています。
イベントなども、コロナと上手に付き合いながら少しずつ行われています。
さて、そのような中でも、4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法の適用が中小企業にも始まります。
いわゆる『同一労働同一賃金』ですね。
この法律では、次のように、正規労働者と非正規労働者不合理な待遇差を禁止しています。
均衡待遇: (1)職務の内容、(2)変更の範囲、(3)その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止する
均等待遇: (1)職務の内容、(2)変更の範囲が同じ場合には差別的取扱いを禁止する
また、実務的な対応としては、非正規労働者は、「正規労働者との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができ、事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならなくなりました。
事前準備としては、下記の手順で進めていきましょう。
① 社内で非正規労働者を雇用しているか確認
② 雇用形態ごとに、賃金(賞与・手当を含む)や福利厚生などの待遇について、正規労働者と比べて取り扱いに違いがあるかの確認
③ 待遇差があれば、その差に対し、働き方や役割の違いに見合ったものであるか、不合理でないかを確認
④ 不合理といえない場合は是正
もはや猶予はありません。
『企業は人なり』という言葉もあります。
人財は大切な経営資源ですので、経営活動に活かしていくことは大変重要なことです。
当事務所では、同一労働同一賃金についての支援も行っております。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
福岡は、5月14日に緊急事態宣言の解除が行われ、5月25日に全国的に緊急事態宣言の解除が発表されました。
この解除を受け、一気に交通機関の乗客者は増え、オフィス街にも人が戻ってきたように感じます。
事務所のポストにも6月初旬に、アベノマスクが投函されていました。皆さんはアベノマスク、使ってますか?
さて、コロナ禍で急速に普及したテレワークですが、以前から実施が呼びかけられている制度でした。
しかし、導入している企業は少なかったように思います。
制度としてはあっても、実施されておらず、今回期せずして実施に踏み切られた企業が多かったことと思われます。
テレワークの実施により、業務の明確化、担当者の明確化、責任の所在、コミュニケーションの取り方など、様々な課題が出てきています。
どうしても非対面の時間が長くなることから、日本人の得意とする空気を感じるということが困難になります。
従業員も業務の進捗を適宜報告する、管理者も部下の状況把握、適切な指示、問題が起こる前に相談を行いやすい雰囲気づくりなど、今まで求められてきたものと異なるものが求められるようになってきています。
このような状況の中で、企業が求める能力やスキルはどういったものでしょうか。それは、今まで評価対象としてあった能力やスキルと同じでしょうか?
テレワークが「ニューノーマル」となってきています。このニューノーマルに適応、対応できるような企業支援を行っていきます。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
最近、ネットニュースにあがっていましたトロッコ問題。
合理性と道徳心のジレンマの思考実験だそうですが、合理性とは一体何なのでしょうかね?
さて、今回は合理つながりで、『働き方改革』の同一労働同一賃金編です。
2020年4月1日より「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が施行されました。(中小企業の適用は2021年4月1日)
準備はお済みでしょうか?
ポイントとしては下記の2点です。
①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
資料出所:パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書
この「不合理な待遇差」というのは、均等と均衡を実現することで生じませんよと、厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」に記載されています。
均等とは、前提条件が同じ場合には同じ取り扱いをすること。
均衡とは、前提条件が違う場合には違いに応じた取り扱いをすること。
ガイドラインでは具体的な検討の方向性を例として掲載していますが、
やはり、すべての会社に対応しているものではないため、
基本給や賞与、手当など想定されるあらゆる待遇について、性質・目的に照らせばどうなのかと
きちんと検討しておくことが必要です。
来春には中小企業にも適用が始まります。
これを機に、不合理ではない賃金制度、人事労務管理制度の作成や見直しを考えられている会社も
多いかと思われますが、このような制度は、会社の将来を見据えながら決定していくことが大切になります。
ポイント2項目がきちんと果たせるような状態で施行を迎えることができますよう
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
~編集後記~
働き方改革がテーマなので旅行の写真をアップしてみました
カテゴリー
月刊アーカイブ
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月