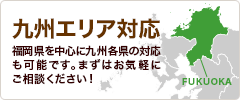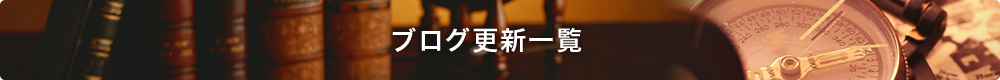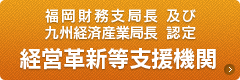経営改善ブログ
もういくつ寝ると~お正月ですね。
本年最後のブログになります。
私自身、福岡県中小企業診断士協会の会長を務めているということもあり、福岡県中小企業診断士協会の一年を振り返ってみたいと思います。
今年は、福岡専門職団体連絡協議会(専団連:福岡さむらいネットワーク)の当番会として代表理事を努めさせていただきました。
10士業間連携のもと、中小企業の支援に対しワンストップサービスをご提供できる機会が増えていっております。
また、今年も11月に「中小企業診断士の日」シンポジウムを開催し、行政、支援機関や他士業および金融機関との連携の強化を図ることができました。
そして同じく、11月には「第9期中小企業診断士登録養成課程」を開講いたしました。
中小企業診断士の養成機関は、九州では初めての開設であり、各都道府県中小企業診断士協会が運営母体となるのは、全国でも初めてとなっています。
九州ではまだまだ中小企業診断士が不足している状態です。
今後は更に、中小企業診断士の能力向上と共により良いサービスを提供できる様努め、実践的な経営アドバイスを行うことのできる中小企業診断士の育成にも努めていく所存です。
また、今年は、中小企業診断制度ができて77周年の大きな節目となった年です。
我々、中小企業診断士は、経営の専門知識を活用し、行政・支援機関・金融機関等と連携して、中小企業への施策の適切な活用を支援するなど幅広い活動を行い、国家資格者としての社会的使命を果たすという役割を担っています。
その責務を果たすべく、来年も更なる飛躍を目指してまいりたいと思います。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
近年、中小企業の経営者から「もう続けるのは難しい」「後を継ぐ人がいない」という相談が急増しています。
こうしたとき、多くの経営者が思い浮かべるのは「休業」、「廃業」という選択肢です。
しかし実際には、“会社を閉じなくてもいい道”があります。
それが第三者承継と言われるM&Aによる「事業譲渡」や「株式譲渡」です。
廃業は、会社を完全に清算して終わらせる手続きです。
一方、M&Aは、会社や事業を他社に引き継いでもらう「バトンタッチ」であり、事業承継の出口戦略のひとつです。
この違いは大きく、廃業では資産を処分して現金化するのに対し、M&Aではその事業そのものに“価値”が付きます。
つまり、廃業ではお金が出ていく一方、M&Aではお金が入る こともあるのです。
M&Aの対象になるのは、単に利益を出している会社だけではありません。
たとえば、
・安定した顧客基盤や取引ルート
・継続的な許認可や資格
・人材や技術力
・地域での信頼・ブランド
これらも「価値ある資産」として評価されます。
成功のカギは「早期相談」と「正しい準備」です。
会社を売却するには、財務状況の整理、契約関係の確認、在庫や資産の明確化など会社の可視化が必要になります。
廃業を検討する段階で動き出すことが、最も良い条件での譲渡につながります。
一方、頑張りすぎて資金繰りが限界に達してからの相談では、選択肢が大きく減ってしまいます。
当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援や休廃業支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
経営者の想いを大切にしたM&Aをサポートしています。
「会社を誰かに引き継いでほしい」「従業員を守りたい」
その想いがあれば、まだ廃業ではなく再生のチャンスがあります。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
自主廃業は経営者主導で事業を清算する方法、法的整理は裁判所の関与のもとで債務整理を行う手続きです。主な違いは「裁判所の関与の有無」と「債務整理の方法」にあります。
自主廃業(任意整理)とは?
自主廃業とは、会社や個人事業主が自らの意思で事業を終了し、債務や資産の整理を行う方法です。裁判所を介さず、経営者が主導して進めます。
特徴
- 裁判所の関与なし:手続きが比較的簡便で柔軟。
- 債務が少ない場合に有効:債権者との信頼関係があるとスムーズ。
- スピード感がある:行政手続きや契約解除、在庫処分などを迅速に進められる。
- 費用が比較的安価:弁護士費用や裁判費用が不要な場合が多い。
注意点
- 債権者との調整が必要:合意が得られないとトラブルに発展する可能性。
- 債務整理の法的強制力がない:一部の債権者が強硬な場合、対応が難しい。
法的整理とは?
| 手続き名 | 概要 | 主な対象 |
| 破産 | 債務超過で返済不能な場合に、裁判所が資産を処分して債権者に配当する | 清算型 |
| 特別清算 | 株式会社が清算する際、債権者の同意を得て裁判所の関与のもとで進める | 清算型 |
| 民事再生 | 事業を継続しながら債務を整理し、再建を目指す | 再建型 |
| 会社更生 | 主に大企業向けの再建型手続き | 再建型 |
特徴
- 裁判所の関与あり:手続きに法的強制力がある。
- 債権者の権利が制限される:差し押さえや強制執行が停止される。
- 透明性が高い:公的な手続きのため、利害関係者にとって安心感がある。
注意点
- 手続きが煩雑で時間がかかる:書類作成や裁判所とのやり取りが必要。
- 社会的信用への影響:破産などは「倒産」として報道されることもある。
- 費用が高額になりやすい:弁護士費用や裁判費用が発生。
どちらを選ぶべきかは、債務の状況、関係者との関係、再建の可能性などによって異なります。専門家(弁護士や中小企業診断士)への相談が重要です。
当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援や休廃業支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
今年も残り3ヶ月になりました。
9月は業務多忙のためブログの更新が出来ませんでしたので
10月は2回ブログを更新したいと思います。
今月は中小企業の休廃業の現状について述べてみたいと思います。
2025年の中小企業の休廃業は過去最多ペースで進行しており、年間7万件超に達する見込みです。特に「黒字廃業」や「円満な廃業」が増加しています。
以下に、最新の動向を詳しくまとめます。
・2025年1〜8月の休廃業・解散件数は全国で47,078件。前年同期比で約9.3%増加し、年間7万件超のペースで推移。
これは、2016年以降で最多だった前年をさらに上回る見込みです。
・休廃業した企業のうち、直近損益が「黒字」だった割合は49.6%と、初めて5割を下回りました。
・「資産超過型」(債務より資産が多い)の企業は64.1%と過去最高。つまり、経営に余力があるうちに事業を畳む「円満な廃業」が増加しています。
・経営者の平均年齢は71.65歳。最も多い年齢層は「70代」(39.6%)ですが、「50代」「60代」の廃業も増加傾向。
後継者不在や健康問題が廃業の大きな要因となっています。
・最も多いのは建設業(5,938件)、次いでサービス業(5,884件)、製造業(2,289件)。
特に「生命保険代理店」などの小規模業態で廃業が急増。競争激化や規制強化が背景にあります。
以上が今年の動向ですが、2020〜2022年は給付金や助成金で休廃業が抑制されていましたが、2023年以降は支援策の縮小、物価高騰、人手不足などが重なり、廃業が加速しており、将来の業績悪化を見越して、「あきらめ廃業」を選ぶ企業も増えています。
中小企業は「事業継続」か「円満な廃業」かの選択を迫られています。
M&Aや事業承継支援、廃業後の生活保障など、官民による支援策の充実が求められています。
当事務所も中小企業庁登録の「M&A支援機関」として、中小企業のM&A支援や休廃業支援を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
[2025.8.23]
カテゴリー:中小企業診断士
8月も終盤ですが、毎年8月の第1土曜日、日曜日の2日間にわたり中小企業診断士国家試験の1次試験が実施されています。
中小企業診断士は、昭和27年に登録制度が制定され、昭和38年からは旧試験制度が導入されていました。
その後、平成13年に試験制度等の大幅な見直しがおこなわれ、さらに5年後の見直しを経て、現在の試験制度になっています。
中小企業診断士になるには、1次試験合格後に大きく二つのルートがあります。
1次試験、2次試験合格後に実務補修又は診断実務従事を経て、中小企業診断士登録する第一ルート、
1次試験合格後、登録養成機関等の行う養成課程を修了し中小企業診断士登録する第二ルートです。
中小企業診断士に必要な学識を問うものであるため、1次試験は全員が受験しなくてはなりません。
今年は8月2日、3日の二日間にかけて行われ、経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策の7科目と多岐にわたっています。
1次試験の受験者申込者はここ数年2万人を超え、昨年は2万5千人強と過去最高でした。
今年も昨年並みの受講申込のようです。
また、中小企業診断士に必要な応用力を判定する筆記試験及び口述試験の2次試験があります。
2次試験の受験者は、ここ数年8千人前後のようです。
第一ルートで中小企業診断士になられる方は、受験者数のおよそ4%前後と狭き門となっています。
また第二ルートでは、登録養成課程を修了することにより、2次試験と実務補習が免除されます。
現在、福岡県中小企業診断士協会は九州で初の登録養成機関を運営しており、今年11月開講の受講者の募集を開始しています。
私的な考えですが、資格を得て独立開業して経営コンサルタントとして中小企業の支援をしたいのであれば、登録養成課程を選択されることは、試験では学ぶことができない多くのメリットがあると思われます。なぜなら、受講者には、同じ志を持った受講生が集まるので同じ目標に向かって切磋琢磨する事による学びがあります。
また、働きながら1年間で修了できるというメリットもあります。
中小企業診断士は『中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家』です。
また、中小企業診断士は民間のコンサルタントの中で唯一、国家資格を与えられている存在です。
中小企業診断士は、複雑化・高度化している小規模企業の経営支援ニーズに対する従来の中小企業支援の担い手として、専門的知識をもってアドバイスしなくてはなりません。
受験者の方は、ぜひ登録養成課程も一つの選択肢としてご検討してみてください。
カテゴリー
月刊アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月