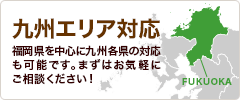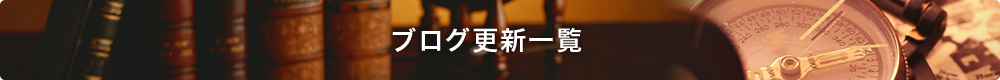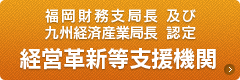経営改善ブログ
最近、新聞紙上でもコロナ融資の返済が本格化してきて中小企業は生き残りをかけて正念場を迎えていると言われています。
確かに最近は企業再生や経営改善についての支援依頼も増えてきています。
継続支援のために銀行から「経営改善計画書」を策定して欲しいと言われても、その真意を良く理解していない経営者がほとんどのようです。
銀行によって多少違いはありますが、銀行は融資先企業を債務者区分によって下記のようなランク分けを行なっています。
「正常先」・「要注意先、要管理先」・「破綻懸念先」・「実質破綻先」・「破綻先」です。
そして、いわゆる不良債権とは、このグループ分けで「要管理先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」が該当します。不良債権というと「破綻先」など完全に倒産している債務者をイメージしがちですが、不良債権先のほとんどが普通に営業している先です。
しかし銀行の対応としては、「要管理先」にランクされると新規の無担保融資は厳しくなり、「破綻懸念先」にランクされると新規の融資そのものが厳しくなるのが現実です。また「実質破綻先」以下ではたとえ事業を継続している場合でも債権回収が優先されます。
したがって、銀行から融資が積極的に受けられる企業は、「正常先」に該当する企業であるといえます。
「正常先」の企業であっても、その業況の変化により不良債権に転落します。その道筋を理解することは、決算書を見るうえで重要なことです。
たとえ今が「正常先」であっても、経常利益段階で赤字を計上したとします。銀行は、1期だけの赤字若しくは2期連続であってもコロナ禍のような特殊な事情があった場合は、一過性の赤字と判断し、債務者区分を「正常先」にとどめます。
しかし3期連続赤字となった場合は、一過性とはいえなくなり「その他要注意先」にランクダウンします。
「その他要注意先」となった企業が、さらなる業況悪化により、銀行に借入れ返済額の軽減の条件変更を申し出たとします。
すると融資の条件変更という事象により、その企業は「要管理先」にランクダウンとなり、不良債権の仲間入りとなってしまいます。このようにいとも簡単に不良債権になってしまうのです。
しかしこれでは世の中の景気変動により不良債権だらけになってしまいます。そうなると銀行は大幅に引当金を積み増さなければならず、体力のない銀行は経営状態が苦しくなってしまいます。
そこで不良債権とならないための逃げ道が用意されています。それが「経営改善計画」の策定です。ですからもし経営者が銀行から「経営改善計画を策定してください」と言われたら、自身の企業は不良債権一歩手前の段階にあると認識してください。
この場合、たとえ条件変更を行っても銀行が適切と判断する経営改善計画を策定することができたら、企業は不良債権である「要管理先」にランクダウンすることなく、「その他要注意先」にとどまることになります。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
5月も半ばを過ぎて暦の上ではもう初夏となりました。
日頃、経営コンサルタントとして中小企業の経営者や幹部の方に対して経営計画の策定支援を行なっていますが、その過程で「目的と目標」の違いを良く理解されていないケースが見受けられます。
今回のブログのテーマは、そんな知っているようで良く理解できていない「目的と目標」の違いについてです。
まず、結果を出すために知っておきたい、目的と目標の違いは7つあります。
違い1. 目標は目的のためにある。
違い2. 目標は具体的に、目的は抽象的に。
違い3. 目標は見えるモノ、目的は見たいモノ。
違い4. 目標は過程、目的は行き先。
違い5. 目標は複数、目的はひとつ。
違い6. 目標は諦めても目的は諦めてはいけない。
違い7. 目的は目標の先にある。
如何でしょうか?
分かるようで分からないでしょうか?
要約すると、「目標」とは、単に目指すべき状態(計画として定量的・定性的に表すことが可能)や目指すべき具体的なものをいいます。そして、それに意義(目指す理由や意味)が付加されることにより「目的」となります。意義とはそれを目指す理由であり、その行為に自分(あるいは会社)が見いだしている価値や動機のことです。
目的と目標の関係を数式で表すと
目的=目標+意義
になります。
実際のところ、会社において仕事や業務の目的に代わって目標を置くことはできます。
しかし、その時に意義が欠如していると、社員にとっては「目標疲れ」が生じる危険があります。実は、向かう先に意義を感じていないがための目標疲れであることが多く、あるいは手段が目的になってしまうことが多いのです。
ですから、経営者は目標に意義を加え、目的に昇華させ、社員と共有する必要があるのです。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
先月のブログでも少し触れさせていただきましたが、令和4年4月より、全国47都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会を関連機関(経営改善支援センター)と統合し、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する組織として「中小企業活性化協議会」が設置されました。
また、それに合わせて「中小企業活性化協議会」による事業再生等の支援とともに、民間による事業再生等の支援を促進するため、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく私的整理を支援する制度が創設(4月15日から開始予定)されました。
この他にも、経済産業省・金融庁・財務省が連携して「中小企業活性化パッケージ」として、ポストコロナを見据えて中小企業を支援する様々な施策が発表されています。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006.html?msclkid=0e790994bc9c11ec84dc082a58518f6d
国もやっと、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援に本腰を入れるようです。
当事務所も「経営革新等支援機関」として、今回の支援策を活用しながら微力ではありますが、地域経済活性化のお手伝いをさせていただきます。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
遅くなりましたが、本年も宜しくお願いいたします。
今年、第1回目のブログです。
昨年も、一昨年に引き続きコロナに翻弄された1年でした。
ご存じの通り、年明け早々にオミクロン株の爆発的な拡大に伴い、多くの都道府県で
「まん延防止等重点措置」が適用されています。
この新型コロナの影響で、窮境に立たされている中小企業は本当に数多く存在しています。
政府もこの2年間近く、中小企業の資金繰り対策としてコロナ融資を断続的に行なってきましたが
据置期間も終わり、元金返済も始まっています。
一部の業種ではコロナ禍以前の水準に回復した企業もある一方、出口の見えない企業も多く存在しています。
そのような企業は、現状として過剰債務状態であり、コロナ禍以前の業績に回復しても
約定弁済が出来ない企業が存在します。
そのような企業の支援を日々行なっていますが、経営者本人が「財務と会計」の違いを理解していない
ケースが多く見られます。
また、将来の経営判断に必要な「管理会計」について、認識のない経営者の方も大変多いです。
そのような、「財務と会計」の違い、「管理会計」について、来月のブログで詳しくご説明したいと思います。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
12月も半ばを過ぎ、福岡でも初雪が観測され冬本番となりました。
今月のブログは、最近の補助金の要件となっている、「付加価値額」を取り上げてみたいと思います。
「付加価値額」とはなじみの無い言葉だと思いますが、経済産業省の各種補助金では付加価値額の一定以上の増加が
要件となっており、下記のように定義されています。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
人件費とは、全従業員(非常勤含む)及び役員に支払った給与等(給料・賃金・賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費・法定福利費や退職金は除く)等です。
また、営業利益+減価償却費はいわば本業でいくら現金を得たかを表す指標であり、簡易FCF(フリーキャッシュフロー)としても財務分析等に活用されています。
つまり、付加価値額とは会社の本業での現金収入と人件費を合わせたものであり、付加価値額の増加とは
以前より本業での現金収入が増え、人件費もより多く支払うと言う状況です。
今年度はコロナ禍にもかかわらず、最低賃金が大幅に引き上げられました。
付加価値額は、このような国の施策を反映している指標とも言えます。
ただ、中小企業の現状としては大半の会社が人件費を大幅にアップできる状態では無いと思います。
安部中小企業診断士事務所は、“100年続く企業”を応援しています。
カテゴリー
月刊アーカイブ
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月